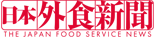Contents
型破りのクラフトビールサーバーかく生まれり 「タップ・マルシェ」は業界にイノベーションを起こすのか
「多品種少量」実現し簡便さも 厨房からホールのサーバーへ
昨年の首都圏と全国の一部店舗での試験販売を経て、いよいよキリンの戦略製品「タップ・マルシェ」が全国展開を本格化する。クラフトビールの世界を飛躍的に拡大する可能性を秘めた、いわば「イノベーション」といっても過言ではない同製品は、一体、どのように生まれ、どこへ向かおうとしているのだろうか。その深部に迫った。
ペット容器すぐ決定 難問題は容量の設定
 時は3年半前に遡る。マーケティング部企画担当(現・企画部主査)だった上田隆史さんは、「ヤッホーブルーイングと提携し、会社としてクラフトビールをやり始めたが、一緒になってプラス効果を生んでいくイメージがしづらく、自分としては腑に落ちていなかった。では、どういうことをやったらヤッホーと面白いことをできるか。そんなことを真剣に考えていた」という。
時は3年半前に遡る。マーケティング部企画担当(現・企画部主査)だった上田隆史さんは、「ヤッホーブルーイングと提携し、会社としてクラフトビールをやり始めたが、一緒になってプラス効果を生んでいくイメージがしづらく、自分としては腑に落ちていなかった。では、どういうことをやったらヤッホーと面白いことをできるか。そんなことを真剣に考えていた」という。
クラフトビールの現状をリサーチしてみると、業務用生樽はサイズが大きいが、クラフトビールの場合は、タップ数がある程度多くないと楽しくない。それを実現するとなると、必然的に投資も大きくなるばかりか、都心のよほどの繁盛店でない限りは、消費スピードが落ちることで提供時品質も落ちてしまう欠点があった。
そうした「欠点」をもし改善できるとしたら、「おもしろいことができるのではないか」と、上田さんは漠然と考えていた。 これまでキリンビールが長年取り組んできた生産効率化の流れとは逆行するが、クラフトビールの商いは種類が多くないと成立せず、そのためには量目を減らすことが必須条件だった。キリンビールの大樽の中で一番小さい樽でも7L。これでも多いと上田さんは考えていた。
挑戦するのは「多品種少量でなおかつ店舗での取り扱いが簡便なこと」。さらにコストの壁もある。そうした制約の中で、新たな容器を開発しなければ、「おもしろいこと」は実現できない。それを実現するために、上田さんはその後、多くのことを「捨てる作業」から入らなければならなくなる。 今からほぼ3年前の2015年1月。キリンビールの社内では、クラフトビールの今後のあり方を模索している最中で、ちょうどクラフトビールを盛り上げていくための分科会設立が検討されていた時期だった。
上田さんは同じマーケティング部で商品開発研究所に所属していた土屋義徳さん(現・マーケティング部商品開発研究所所長)と2人で、クラフトビールに関して雑談をしていた。上田さんはその雑談を元に、A4の紙1枚に手書きで、「およそ通常の企画書とは言い難い体裁の企画書」を書き上げて、当時のキリン株式会社の企画部(現・キリンビール企画部)に話を持って行った。その企画案が通り、翌2月に分科会の立ち上げが許されたのだった。 購買した原材料などに対し各プロセスで価値(バリュー)を付加していくため(=バリューチェーン)、上田さんの分科会には生産系の社員も加わり、6人で原案を揉んだ。
2カ月間で仕上げた原案を3月末には経営陣に答申し、15年8月に正式にプロジェクトチームが発足した。上田さんと生産系のメンバーが専任となり、各ジャンルのプロフェッショナル5人が兼任で計7人のチームが立ち上がった。 その中にはパッケージ研究所のメンバーもおり、「炭酸ガスが抜けないペットボトルの特許技術をビジネスに活かしたい」と温めていたメンバーもいた。
さまざまな容器が俎上(そじょう)に載せられたが、社内にこうした独自の技術があったことから、「比較的早い時期にペット容器を使用することが決まった」という。 確かに、ペットボトルは軽いため、ハンドリングがいい。女性のアルバイトスタッフでも容易にビールの入れ替えが可能だ。そして何より、リターナブルの樽容器と異なりワンウエイで出荷できるため、事業ゴミで出すことができる。さまざまな面で飲食店のオペレーションが飛躍的に軽くなる点は魅力だった。
問題は容量だった。どのくらいの容量にするのか。例えば2L容器であれば、既存の金型があるのでコストは下がる。この容量問題については「侃々諤々(かんかんがくがく)の議論がなされた」という。プロジェクトチームでの議論の結果、開栓後、1週間を目安に提供し終わることを念頭に置いた。 主要なクラフトビール取扱店などで販売動向を調査し、その結果、250mlをターゲットボリュームとし、1週間で12杯を提供するというシミュレーションに辿り着いた。最後まで、「2.5L=10杯」と「3L=12杯」で迷ったというが、「自信はなかったが、昨年の実験店での結果を見る限り、2杯分とはいえ、少ないとハンドリングが面倒になるため、3Lを選んで正解だった」と上田さんは振り返る。
簡便な取扱いが好評 新たなインフラ網へ

プロジェクトチームで開発に携わったキリンビール企画部の上田隆史氏(キリンビール企画部主査)
飲食店1店舗当たりの平均販売リッター数が減少傾向にある中、「どうにかして手を打たなければならない」という事情は、何もキリンに限った悩みではない。ビール大手4社共通の悩みでもある。キリンにしても、この「タップ・マルシェ」を導入することで、1店舗当たりの販売リッター数が伸びるのかどうかは、実際にフタを開けてみるまでわからなかったというのが本音だ。
そもそも、国産の生ビールとクラフトビールを併売している例が極めて少ないため、キリンとしてもシミュレーションのしようがなかったという方が正しいかもしれない。 しかし、同社の実験店舗では、導入後に既存の樽生杯数が7~8掛けになるとはいえ、「タップ・マルシェ」の導入により、全体の杯数はもちろんのこと、売上・利益が導入前より伸びるといった傾向が顕著になった。上田さんが言う。
「通常の国産の生ビールは、お客さんの中で『このくらいの価格』といった絶対価格が存在しているが、クラフトビールにはまだそれがない。どういう形で提供するかはお店側にイニシアチブがある。例えばワイングラスを使い800円で提供するなど、提供方法で店によるブランディングができる点が喜ばれているのではないか」
「タップ・マルシェ」は既存の業務用酒販店ルートとは異なり、飲食店が専用のサイトから発注し、工場直送で店に届く仕組みだが(商流のみ酒販店経由)、そのサイトに容量ごとに6種類程度のグラスを紹介している。業態に応じて選んでもらい、付加価値を載せる提案を飲食店と共に考えているのだという。 地方都市の実験店では、アルバイトスタッフが「タップ・マルシェ」がキッカケとなってお客さんとの接点が生まれ、商品を勧めたり、モチベーションアップにも繋がっている事例もみられる。
こうした現場での効果は、上田さんをはじめとするキリンのプロジェクトチームも想定外だったようだ。 現在、首都圏と全国の一部地域の1200店舗に先行導入し実験を行っているが、「情報格差のなくなったいま、地方の店舗が売上上位に入ることが珍しくない」と上田さんは言う。上田さんの指摘のとおり、都市部との「情報格差」は確かになくなった。インターネットの普及により、情報が拡散するスピードは格段に上がった。しかし、その一方で、都市部とローカルとの「人口格差」は拡がる一方だ。この「人口格差」こそが「タップ・マルシェ」が挑んだ「多品種少量化」と合致する。地方の飲食店の関心を集める理由はそこにもある。
通常の樽生でクラフトビールを品揃えした場合と比較して、「タップ・マルシェ」ならば15分の1~20分の1の在庫で商売が成立するため、東京以外でも受け入れられるという点が、関心を集めている大きな点だ。どんなに良い商品だとしても、樽の大きさが大きすぎれば、人口の少ない地方都市ではどうしても機能しなかったのではないか、との声がキリンの内部からも挙がる。
3Lペットボトル×4タップという、いわば「絶妙」とも言える「多品種少量」の組み合わせが、特に地方の飲食店や、クラフトビールとは一見すると無縁の和食業態などの心をくすぐっていることは間違いない。 参加しているメーカーからも「、自分たちが造ったビールが、造ったときのおいしい状態で提供してもらえる点がすごく嬉しい」との声が挙がる。サーバーには保冷機能しかないため、あらかじめ店の冷蔵庫でボトルを冷やす必要があるが、温度管理に加え、鮮度が落ちる前に使い切れるという点が、クラフトビールメーカーからも評価されているのだろう。