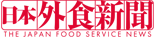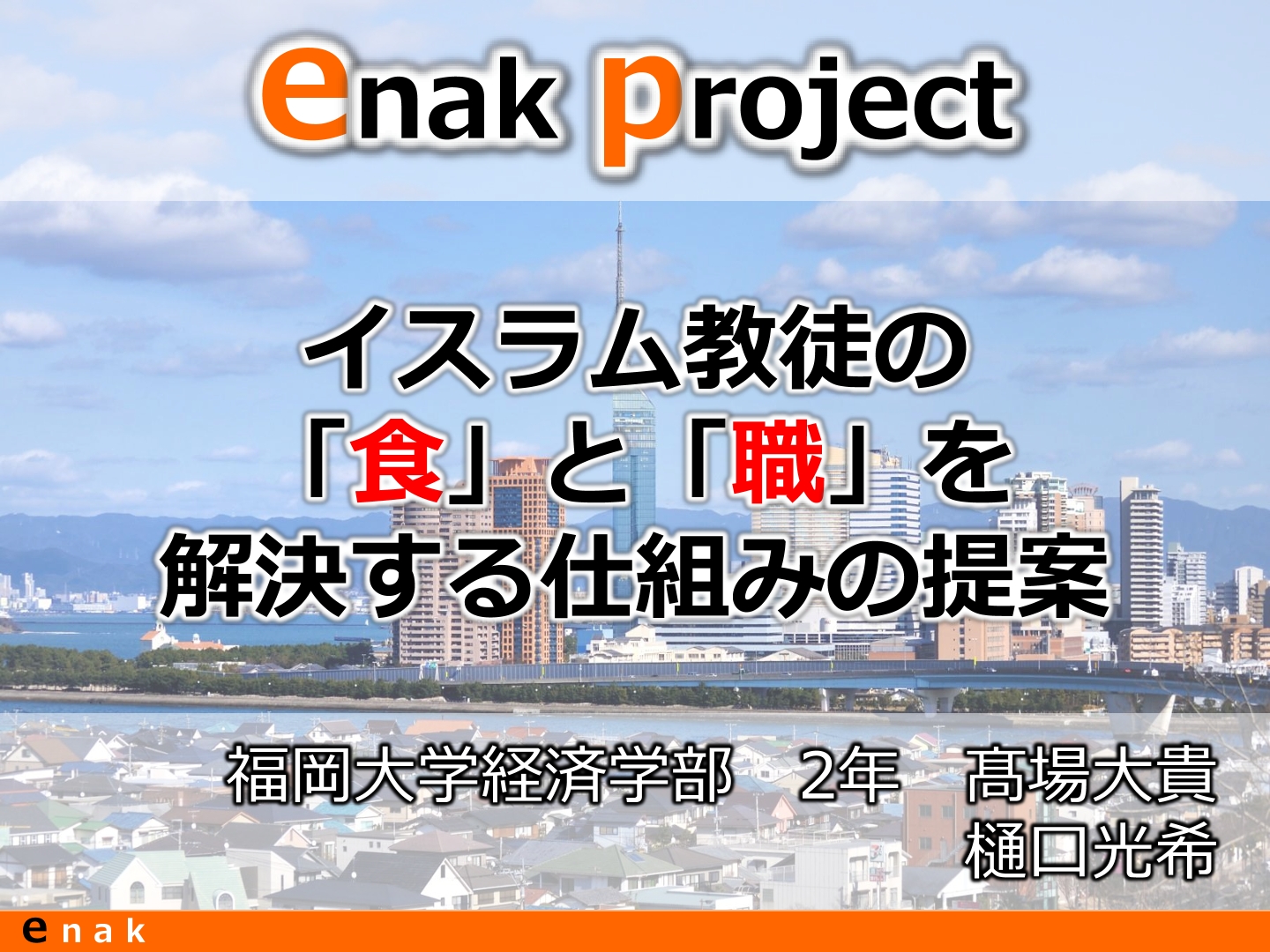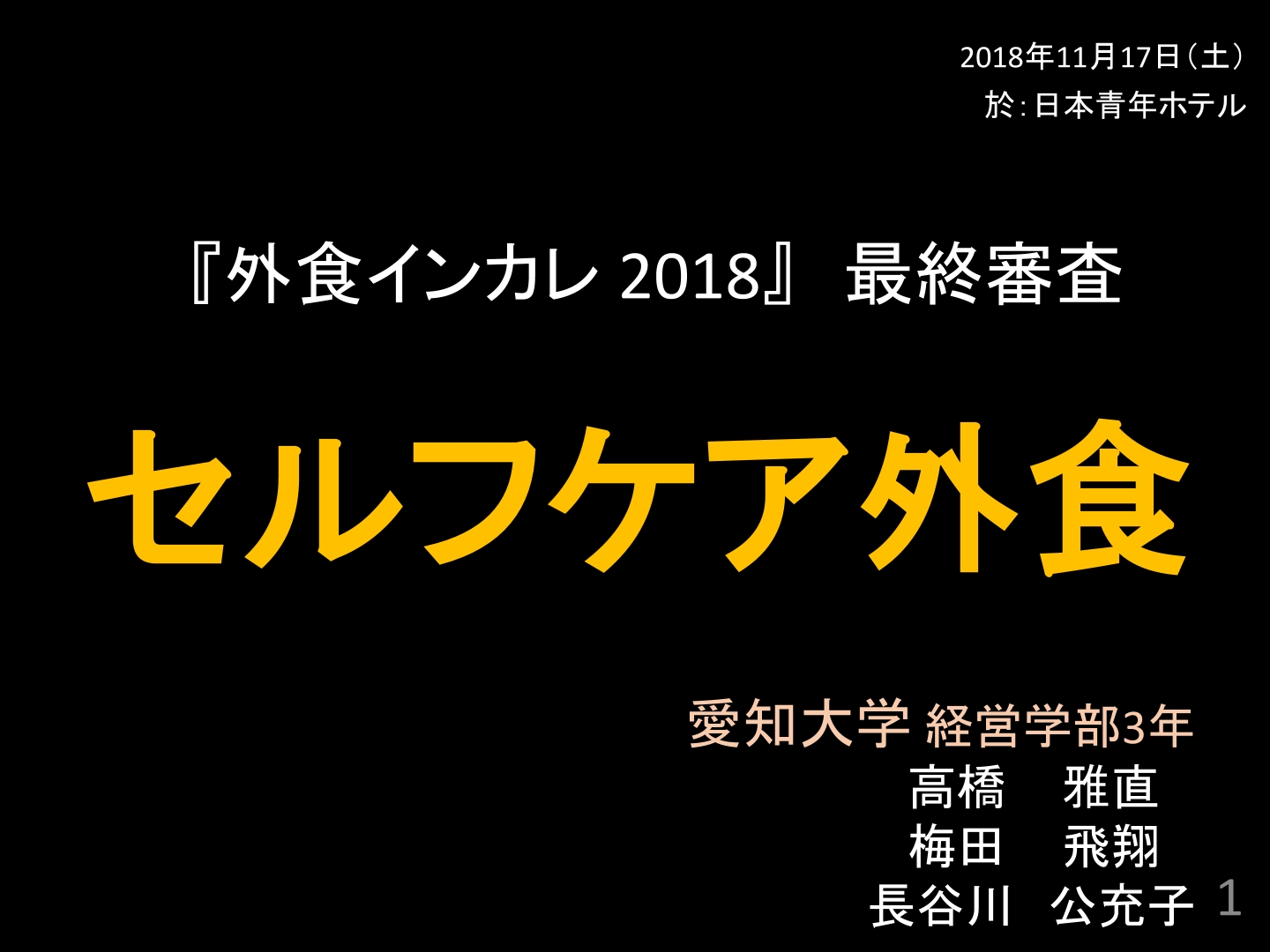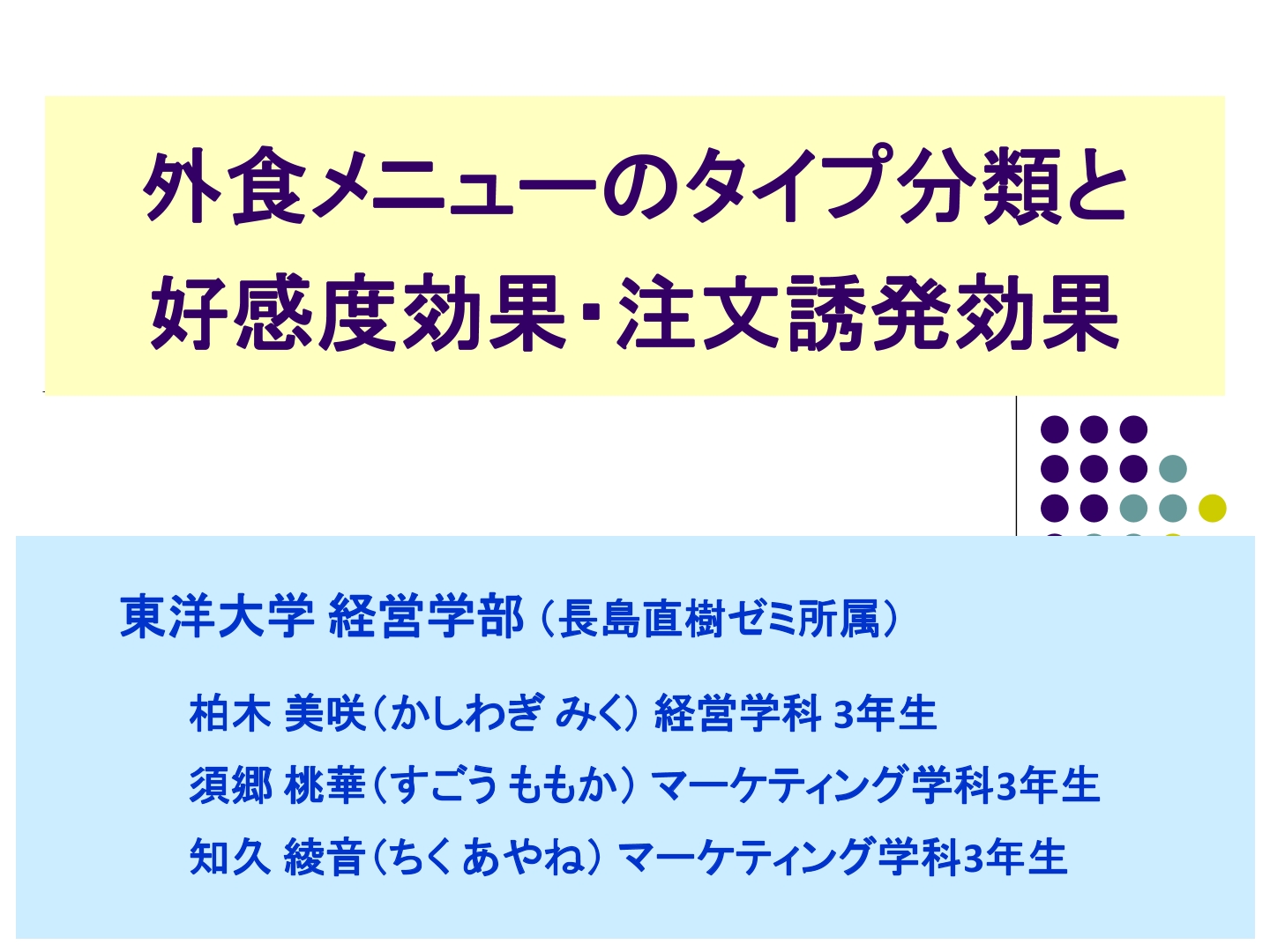前回に続き、日本フードサービス協会(JF)と日本フードサービス学会(JF学会)が昨年、大学・大学院生を対象として開催した初のビジネス・アイデアコンテスト「外食インカレ2018」(秋元巳智雄実行委員長)の受賞者のプレゼン内容を紹介する。
今回は、イスラム教徒が安心して食べられるメニューの開発とイスラム教徒の雇用を両立する認証の仕組みを提案し、銀賞を受賞した福岡大学2回生グループのプレゼンを再録する。
銀賞受賞 「イスラム教徒の『食』と『職』を解決する仕組みの提案」 福岡大学2回生(高場大貴さん・田邊桃佳さん・樋口光希さん)
人口減少で日本経済が衰退することが予想される中、グローバル化が必要となる。そこで私たちはイスラム教徒に注目した。世界人口の20%を占めると言われるイスラム教徒が、訪日外国人に占める割合はたった1.1%。その理由は、食の面などでイスラム教徒を受け入れる体制が整っていないから。  豚とアルコールを含む調味料などが禁止され、牛・鶏肉も特別な処理をされたものに限るなど細かいルールが存在する。
豚とアルコールを含む調味料などが禁止され、牛・鶏肉も特別な処理をされたものに限るなど細かいルールが存在する。
そこで、日本人のイスラム教徒にヒアリング調査したところ、ハラールには世界統一の基準はなく、人によって解釈が異なるグレーゾーンが存在することがわかった。 続いてハラール認証について調べたところ、厳しいハラール基準を要求し、認証機関が利益を得る仕組みとなっていることから、イスラム教徒の間で不信感が広がっているという。
それでは、本当にイスラム教徒が求めているハラール対応とはいったい何なのか。 福岡市にあるモスクのリーダーであるイマーム(指導者)に話を聞いた。イマームは、イスラム教徒に対して大きな影響力を持ち、イマームの判断でハラールかどうかを証明できる存在。そこでグレーゾーンを明確にするために、食に関する三つのイベントを開催した。 
まず、ハラール対応の日本食試食会を開催した。使った食材31品はイマームのチェックを受け、かき揚げや親子丼などを作って提供した。
続いて、イスラム教徒の人と一緒にハラール対応の日本食調理会を実施し、最後にハラール食品の開発と販売を手掛けた。みりんを水あめに、醤油をノンアルコール醤油で代用したハラールちまきを1個400円で販売したところ、2日間で98個売れ、そのうち23個はイスラム教徒が購入した。メディアなどでも取り上げられ、好評だったことから販売継続も決まった。
これらのイベントを通して、多くのイスラム教徒から生の声を聞くことができた。そこで、日本食への関心が高いにもかかわらず、今まで日本食を食べていなかった理由をアンケート調査した結果、メニューが英語表記ではないことと、ノンポーク、ノンアルコールかどうかを聞いても店員が答えてくれないという回答が半数を超えた。その対応として私たちはメニューを英語表記とし、調味料は成分表示まで写真で掲載した。
その結果、27人中25人が安心して食べられたと回答。ハラール認証がなくても、イマームが監修したことが大切なのだと気付いた。
 さらに私たちはイスラム教徒の「食」と「職」を解決する仕組みを考えた。飲食店は人材不足、イスラム教徒は就職が課題となっている。そこで、飲食店がイスラム教徒を雇用すれば、人材不足対策となり、ハラール対応も普及するのではないだろうか。また、イスラム教徒が祈りをささげて屠殺すればハラール肉になるため、イスラム教徒を屠殺所で雇用すれば、ハラール肉の製造もできる。
さらに私たちはイスラム教徒の「食」と「職」を解決する仕組みを考えた。飲食店は人材不足、イスラム教徒は就職が課題となっている。そこで、飲食店がイスラム教徒を雇用すれば、人材不足対策となり、ハラール対応も普及するのではないだろうか。また、イスラム教徒が祈りをささげて屠殺すればハラール肉になるため、イスラム教徒を屠殺所で雇用すれば、ハラール肉の製造もできる。
ハラール食品を流通させるためにイマームと連携し、イマームがノウハウを提供し認定した食品にQRコード付きのイマームマークを発行。イマームマークがついた食品や飲食店をサイトで公開し、そのサイトでは、成分表示とトレーサビリティーを徹底する。
また、レビュー、評価機能も搭載することで、イスラム教徒の口コミを判断基準にできる。この情報をメーカーや飲食店にもフィードバックすることで、情報発信、情報収集、集客ができる多言語対応のサイトとなる。
 飲食店が個別に認証を受けるハラール認証とは異なり、信頼できるイマームマーク食品の専門卸売業者を設置することで、卸業者と飲食店が一体となって取り組めるのではと考えた。実際に福岡市のスーパーマーケットに提案したところ、快く引き受けてもらえ、現在準備を進めている。
飲食店が個別に認証を受けるハラール認証とは異なり、信頼できるイマームマーク食品の専門卸売業者を設置することで、卸業者と飲食店が一体となって取り組めるのではと考えた。実際に福岡市のスーパーマーケットに提案したところ、快く引き受けてもらえ、現在準備を進めている。
また、福岡市の高島宗一郎市長にも活動を報告したところ賛同を得た。 私たちはイスラム教徒の雇用、イマームマークの発行とサイトの活用、ハラール専門の卸売業者の三つのポイントを踏まえて、地域全体でハラール対応に取り組む。その後、このノウハウとシステムを全国に発信し、アレルギー対応、ベジタリアンにも応用していきたいと考えている。
日本外食新聞2019年3月15日号掲載