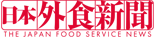日本酒の消費量が減り酒蔵も減少傾向になる中、近年は若い人にも受け入れられるよう、新たな感覚を取り入れた日本酒も増え、日本酒をメニューに入れる店舗も広がりを見せている。一方で、来店客がその魅力を十分に理解できているとはいえず、「ランキングや話題性だけで選ばれている」と感じる現場の声も多いという。
そこで神奈川・大船で居酒屋「涛司(とうじ)」を運営するハイル(神奈川・横浜、清水絋太郎社長)が、業態歴3年以上の居酒屋・和食店経営者、店長、料理長を対象に実施した「提供する日本酒の価値」調査で、約8割が「ペアリングを提案することで顧客満足に貢献している」と回答した。同調査は6月10~12日にインターネットで実施され、510人から回答を得た。
お客さんから「『料理と合うお酒を教えてほしい』とリクエストされることはあるか」の質問では、「よくある」(32.2%)と「たまにある」(56.9%)を合わせた89.1%が「ある」と回答。日本酒と料理の関係性に対する顧客の関心が極めて高いことがわかった。
「よくある」「たまにある」の回答者に「料理やお酒の内容が変わっても、その都度適切なペアリング提案ができるスタッフの人数」について尋ねたところ、「1〜2人」と「3~4人」の回答で約8割を占めた。同社ではこの結果から、「ペアリング提案が可能な人材の属人化傾向が見られる」としている。
一方で、「ペアリングを提案することは、顧客満足にどの程度貢献していると感じるか」では、「非常に貢献している」(25.3%)と「ある程度貢献している」(54.2%)で79.5%となった。同社は、「ペアリングが料理やサービスと並ぶ、飲食店の重要な価値の一部として認識されていることを示している。単なる味覚体験を超えた『記憶に残る体験』として評価されており、その影響はリピート率や客単価向上にも関係している可能性がある」と分析。
「提供している日本酒の種類」では「10~20種未満」(26.7%)が最多となり、「20~30種類未満」(20.0%)、「1~10種類未満」(18.8%)と続いた。
「日本酒を楽しんでもらうための施策」では、「限定・希少銘柄の導入」(46.9%)が約半数となり、2位が「スタッフによる丁寧な説明・接客」(41.6%)、3位が「蔵元との関係性を活かした直送仕入れ」(39.0%)となった。同社は「ただ銘柄を揃えるだけではなく、そのお酒が生まれた背景や造り手の思いを伝えることで、より豊かな顧客体験を提供しようとする意識が見て取れる」との見方を示した。
「これは飲んでおくべき!と強くおすすめする日本酒銘柄」では、〈久保田〉(30代/男性/神奈川県)、〈獺祭〉(40代/男性/神奈川県)、〈越乃寒梅〉(40代/男性/千葉県)、〈十四代〉(40代/男性/兵庫県)、〈高清水〉(40代/男性/秋田県)などがあがった。
「上記銘柄を選んだ理由」(複数回答可)では、「味・香りが非常に優れているから」(51.0%)、「どんな料理とも合わせやすく汎用性が高いから」(40.4%)、「料理との特定のペアリングで真価を発揮するから」(32.8%)が上位を占めた。
「仕入れを断念したことのある日本酒」(複数回答可)では「十四代」(28.2%)が最も多く、「信州亀齢」(21.4%)、「花邑」(19.6%)と続いた。
「仕入れを断念した理由」(同)では、「安定供給が難しいと判断した」(38.5%)、「価格が高く、原価に見合わなかった」(36.3%)、「仕入れルートが確保できなかった」(33.3%)がそれぞれ30%以上となった。
同社では今回の調査を受けて、「日本酒は単なる商品ではなく『体験価値を伴う商品』として、飲食店にとって重要な意味を持つことが改めて浮き彫りとなった」と総括している。