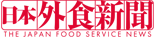外食産業新聞社創業50周年記念特別コラボ企画
日本外食新聞×レストランテック協会/主要経営者インタビュー
アンケートで経営課題見える化
現場力向上の手助けで底上げを
「ファンくる」と言えば、競合他社よりも安価でレポート数が多い覆面調査(ミステリーショッパー)の会社として認知している飲食店が多いだろう。
そして、その調査員はプロではなく、一般人がオフ価格で食事をできるという条件で参加する「お客様目線」が売りでもある。そんな「ファンくる」のイメージとは大きく異なるサービスが、いま飲食業界で注目を集め始めた。その新たなサービスとは一体何なのだろうか――。
※2024年10月15日号「日本外食新聞」の記事を再掲します。記事中の数値などは掲載時のものです
単なる覆面調査会社からの脱却――もはやレッドオーシャンと化しているミステリーショッパー市場で、一定のポジションを確保し続けつつも、これまで培ってきた覆面調査のノウハウを生かして、より飲食店の経営が改善することを、現場発でできないか――それを具現化したのが2024年1月からリリースした「ファンくるC R(Customer Review)」だ。
これは一体、どんなサービスなのか、そして既存の覆面調査は今どういう位置付けになっているのか、代表取締役社長の山口敬人さんがこう説明する。
「来店したお客様の声を分析してどう店舗の改善につなげていけるか。当社はいま、経営戦略の立案から現場のオペレーション改善まで、飲食店の経営を徹底的に支援するというフェーズに入っている。
そのためには、お客様による〝評価視点〟での声から、正確に強み・弱みを浮き彫りにする必要があり、その主軸に店内アンケートを位置付けている。覆面調査は第三者による〝チェック視点〟での詳細項目チェック・画像取得可能な臨店調査ツールと位置づけている。
『多様な調査手法+コンサルティング』を『圧倒的安価×高い納得感』で可視化し、改善につなげる。これを現場レベルで実行できる点が大きな特徴だ」
アンケートでお客様の声を吸い上げることは、アナログのアンケート用紙でも可能だが、グーグルをはじめ、多様なツールの登場により、集計までもが容易になった。しかし、現実には設問の表現や順番を変えるだけでも、得られる情報は大きく変化するのだ。
そして、その集まったアンケートを誰が分析するのか。抽出した課題をどの順番で改善すればいいのか――実は、アンケート調査の結果を自力で分析し、有効に活用できている飲食店は多くはない。つまり、アンケートを実施し、単純な集計結果だけを見て満足している飲食店が大半だということだ。
たかがアンケート、されどアンケート。アンケートは誰でもできるが、飲食企業単独では統計分析をかけるスキルも時間もない。つまり、せっかくアンケートをしても、その結果を活かし切れていないのが実情だ。
いわば、分析のプロがアンケート項目から構築し、ビッグデータとして蓄積された来店客の「生の声」を特許取得済みの独自の統計分析とAI技術を活用して、現場及び経営に落とし込む――それこそが「ファンくる」の新規事業で、主力事業へと急速に成長しつつある「ファンくるCR」なのだ。
その流れを簡単に見ていこう。
まず、①アンケートによって可視化→②課題を特定した上で→③打ち手を立案し→④効果を検証する──店舗が独自にアンケートを行っても、ここまで綿密に落とし込める飲食企業はほぼないと言える。外部の専門家に委託するからこそ、効果検証まで到達できるわけだ。
「ファンくる」はこの事業を立ち上げるに当たり、アンケートの捉え方を一から見直したという。設問を顧客ごとにカスタマイズすることで、一見するとその企業によりフィットした結果を得られそうだが、実はデータ蓄積ができないデメリットがある。
基本的な設問を固定化することで、そのデータを比較・分析できることに気付いたのだ。それにより、評価者の重視する点を数値化できるようになった。これら一連の「経営~現場を支える改善自走プラットフォーム」は数々の特許技術で成り立っているのだという。
この②「課題特定」のプロセスにおいて、店舗別のフィードバック用にアンケート結果を分析した「事業所診断シート」の内容を、見ていこう。